
知っ得百科HOME » くすりと医学 » 和漢薬と医学 » 和漢薬の歴史
和漢薬と医学
和漢薬の歴史
中国医学の三大原典

漢方薬の故郷、古代中国では、各地域に自然と生まれ、伝承されてきた経験的医術があったといいます。黄河地域では、針灸療法を中心とした医学が集大成された「黄帝内経」が前漢時代に編纂されました。さらに後漢時代に中国西方の山地では、伝説上の薬祖神・神農の名をつけた「神農本草経」に薬物の経験的知識が結集されました。さらに、揚子江以南では各地から集めた113種の処方を収載した「傷寒論」が編纂されるなど、時代を経るに従い理論体系を整えていきました。
中国では古くから医薬を業とする者の間で神農信仰が根強く行われていたようです。神農は、中国の伝説上の王で「炎帝神農」とも呼ばれ、自ら草木をなめて薬種を選び、医術を教えたところから医者や薬屋の神となったといい伝えられています。
海を渡って伝播される大陸医学
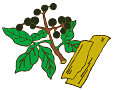
日本では、大陸との交易が盛んになるにつれ、まず中国医学の思想をくむ朝鮮医学が伝えられ、これが中国医学との最初のふれあいとなります。その後、仏教の伝播とともに隋、唐、宋の医学が直接入るようになり、僧の手によって広められます。また、室町時代、安土桃山時代になると、明の時代の中国で体系化されていった「金元医学」の一派を修めた田代三喜や曲直瀬道三が、中国医学の観念的で複雑多岐な医説を整理し、自己の経験を加味して、より実用的で日本的なものへと発展させていきました。やがてそれらは中国の漢薬(中国の生薬)に、日本産の和薬(日本の生薬)を合わせた、和漢薬へと確立されていきました。
富山県の薬業のおいたち
富山県の薬業の歴史については、徳川幕府以前のものは古文書などの説によって一様ではありません。醍醐天皇の時代(927年)の延喜式典薬療によると、越中の薬物として立山付近で熊胆、黄連などを産していたとあります。また、日本医薬の祖は少彦名命といわれますが、その伝方「八心薬」を大伴家で製薬していたことは、史実から明らかだといわれています。
正甫公が始めた越中売薬

富山県といえば、 「越中売薬さん」として全国的にも知られるところ。一般に、富山県の配置家庭薬業は、江戸時代中期、富山藩二代目藩主の前田正甫公の創業と伝えられています。
元禄三年(1690)、正甫公が江戸へ参勤のおり、千代田城内でのこと、福島県岩代三春の藩主の秋田河内守が突然、腹痛で苦しみだしました。そこで正甫公が持っていた「反魂丹」という薬をとり出してすすめたところ、三春藩主はたちどころに回復します。これを見ていた諸藩主は、その薬効に驚いて、正甫公に自分の領内で反魂丹を売り広めることを頼んだといい、これをきっかけに正甫公の奨励のもとで富山県の売薬は全国津々浦々にまで広まったといいます。





