
知っ得百科HOME » くすりと医学 » 和漢薬と医学 » 東洋医学と西洋医学
和漢薬と医学
東洋医学と西洋医学
症状で診る西洋と、証を診る漢方
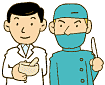
西洋医学(近代医学)では、細胞や組織、体の部位ごとの異常を診断して病名を定め、これに基づいて治療が行われます。対して、東洋医学では全身の不調和を整えるための判定に重きをおき、患者さんの個人差を重視して治療を行います。これを「随証治療」といいます。
「証」とは、頭痛、下痢といった個々の症状を表す言葉ではなく、患者さんが現わす種々の症状を総合的に観察した上で、その患者さんにはどんな漢方薬を与えれば治癒するかを診断するものです。
「証」を決定づける、漢方の物差し
東洋医学の基本思想に、一つの現象を相対する複数の面から見る認識法があります。たとえば、生活体の基本を「気・血・水」という三つの要素から見たり、病態を「陰・陽」、「虚・実」、「表・裏」といった二面から観察していることがあげられます。これらは、証を決定づけるにあたって用いる物差しとなり、さらに患者さん個々によって特定の兆候が加えられて診断されます。
「気・血・水」の調和が健康を保つ
東洋医学では東洋の哲学に由来する「気」という考え方を取り入れています。気とは働きだけあって、形としてとらえることはできないエネルギーのようなもので生体活動に必要なものと考えられています。そして、この気が生体内で生成され、体内を巡ることで生体活動が行われると東洋医学では考えます。
さらに、気が生体内を構築する上で必要不可欠な赤色の体液、すなわち「血」と、気の働きにより生体内を滋潤し栄養を与える無色の体液、すなわち「水」とともに調和を保つことが健康を保つ上で重要であると考えます。
今も元気、血気、病気などの体の状態を表わす言葉があるように、東洋医学では気の異常は血の変調をもたらし、病的状態におちいり、逆に血の異常は気の変調をまねき、病気になると考えられます。このことは気と血が互いに関連し合って生理現象を保っていることを表わしています。
東洋医学では、気血水の不調和は、病的状態におちいるということなので、この三要素のどれが主役かによって、病状が異なり、治療法も違ってきます。
病状をはかる「陽・陰」と「虚・実」
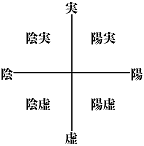
動的なものを(陽)・静的なものを(陰)としたり、表(陽)・裏(陰)、男性(陽)・女性(陰)といったように、自然界の物事や現象をすべて相対する二面から見ようとするのが「陽・陰」です。人も自然界の一部であり、その身体は、体表部(陽)・体内部(陰)、上半身(陽)・下半身(陰)というように分けられます。陽と陰の調和がとれた状態が正しいとされ、どちらが多くても不調和と判断されます。
また、病態をはかる物差しに、もうひとつ「虚・実」があります。「虚」は空虚な状態を表わし、量の不足を意味し、「実」は充実した状態を表わし、量の過剰を意味します。
そして、漢方ではこうした不調和の状態を戻すことが治療であり、「余るものは損じ、不足するものは補う」ということが基本となります。





